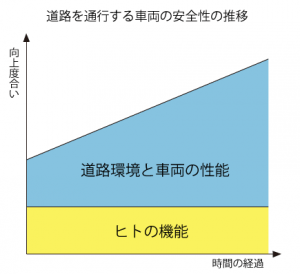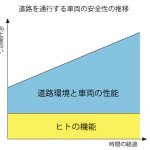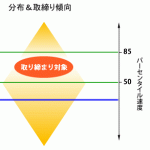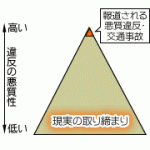交通違反は犯罪ではない
不祥事が多発し、警察威信が地に落ちた2000年、警察組織の問題を改善するために警察刷新会議が召集された。そして、警察刷新会議は、まるで世論が治まるのを待つかのように5ヶ月もかけて「警察刷新に関する緊急提言」をまとめた。
その一方で同年12月、酒気帯び基準の引き下げを織り込んだ道路交通法の改正が異例のスピードで可決された。
そして、今日にいたるまで、ドライバーとライダーを締め付ける怒涛の厳罰化が繰り返されている。それは、酒気帯び運転に限らない。

「交通違反は犯罪だ!」
「悪質な運転は許さない!」
警察不祥事の余韻を打ち消すかのように、取り締まる正義が勇ましくアピールされ続けている。しかしながら、違反と犯罪の区別には、とても重要な意味がある。海外の例として、フランスとアメリカを見てみよう。
- フランス
- 革命後のフランスでは、1808年には犯罪者取扱い法、そして1810年には刑法が作られた。 犯罪者取扱い法によって、強制捜査と、任意捜査が適正に行われるようになり、また刑法では、 crimes(犯罪), misdemeanors(軽犯罪), violations(違反)の3つが明確に区別されるようになった。そして、 この区別は1994年施行された刑法にも踏襲されている。
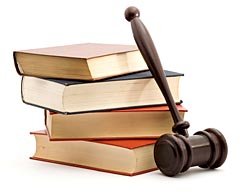 アメリカ合衆国
アメリカ合衆国- アメリカの酒気帯び基準を調べると、必ずといってよいほど “per se law”という言葉が出てくる。これは“それ自体が不法”という使われ方をしている。 つまり、実害をあたえた“犯罪”とは区別されているのである。
二つの国の例は、警察消極目的の原則、警察責任の原則、警察公共の原則、警察比例の原則といった、行政法学が導いた法治国家の基本原則に従っていることを示している。これがニッポンだと、「交通違反=犯罪」となってしまうのである。その結果、次々にシートベルト違反のキップを切る警察官にさえ「正義」が与えられるのだろう。
一方。警察の取り締まりがなければ、悪質な違反で次々の事故を起こすかのように広報されるドライバーとライダーは、たまったものではない。
プリンシプルのない日本
法治国家の原理原則を反故にしてでも、「交通違反は犯罪!」とアピールされているのは、それが単に刺激的で誰もが理解できるなフレーズだからである。プロパガンダと評価されようが、お構いなしにそうした広報を続けているのは、警察不祥事で失った信頼を真っ当な方法で取り戻すのではなく、広報力で警察批判を封じ込める方策が選択されたからだ。
なお、警察刷新に関する緊急提言,第1の1の(3)において、「公安委員会に警察の運営を管理する機能が十分に果たされていない」と指摘されたにもかかわらず、いまだ、警察庁にも都道府県警察本部にも、公安委員会の独自スタッフはひとりも存在していない。それどころか、専用の電話回線さえ保有していない。公安委員会に電話をしても、電話に出るのは公安委員会に管理されているはずの警察官である。このように、公安委員会は独立した組織としての体を為していない。
つまり、公安委員会に組織としての実態を持たせる作業は何も行われていない。うやむやで済ませられたのは、交通事故の恐怖をあおり、それを取り締まる正義を強調することによって、警察の存在価値を高めたからだ。
分かりやすく言えば、正義のヒーローを演じるためには、悪玉が必要であり、警察はヒーローを演じるために、ドライバーとライダーを悪玉にしているのである。